

導体を知る、それは「電気の通り道」を知ること
電気がスーッと流れるものと、全然流れないもの。実はこれ、「物の性質」の違いなんです。このページでは、導体というのは「電気をよく通す物質」ってことを、身近な例や理由とあわせてわかりやすく解説していきます!「どんな素材が導体?」「なんで電気を通すの?」って疑問もバッチリ解決しますね。
|
|
|
導体は「電気が通りやすい素材」

アルミ導体架橋ポリエチレン絶縁電線
6600V架空線に使用されるアルミニウム導体の電線(被覆を剥がした状態)
出典:Photo by Togabi / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より
導体(どうたい)とは、ズバリ電気をスムーズに通す物質のこと。つまり、電気の流れをジャマしない、通り道になってくれる材料なんです。
代表的なものといえば、やっぱり金属。特に銅(どう)やアルミニウムは、家庭の電線などでも大活躍してます。
たとえば──
- 電線の中身:銅が使われてる
- アルミホイル:電気を通すから実験にも使える
って感じ。電気が流れるには「通り道」が必要で、導体はその役目をしっかり果たしてくれるんですね!
なんで導体は電気を通すの?
ここがちょっと不思議なポイント。でも理屈は意外とシンプル!
金属の中には自由に動ける電子(自由電子)がたくさんあるからなんです。
この自由電子たちは、外から電圧がかかると一斉にズラッと動き出します。これが電流の正体!つまり、電子が自由に動ける=電気が流れるってことなんですね。
逆に、電子がガッチリ固定されちゃってる物質は、電気が流れにくい=絶縁体(電気を通さないもの)になります。
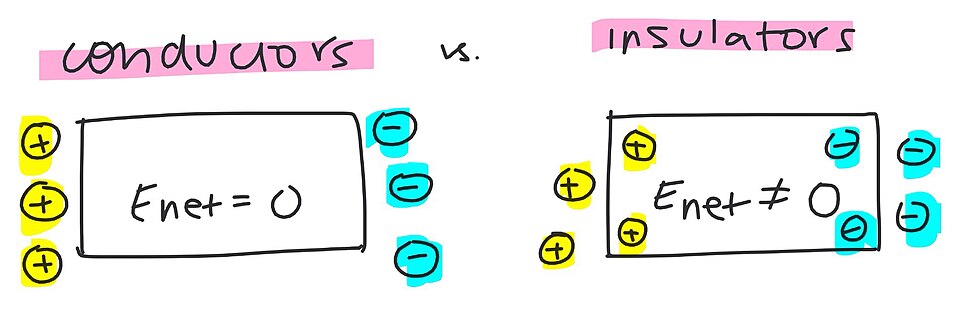
導体(左)と絶縁体(右)の比較図
出典:Photo by Siyer300 / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より
上の図は、「導体(conductor)と絶縁体(insulator)の違い」を、電場(E)の働きという視点からわかりやすく示したものです。
導体(conductor)の特徴(左側)
- 外からプラスの電荷(+)とマイナスの電荷(-)を近づけると…
- 導体の中の自由電子が移動して、外の電場を打ち消すように分布します。
- その結果、中の電場(Enet)は 0(ゼロ)になります。
すなわち導体の中では電場が働かない= 電気がよく流れる性質に繋がっています。
絶縁体(insulator)の特徴(右側)
- 外から同じように電荷を近づけても…
- 電子が自由に動けないため、電場を完全には打ち消せません。
- だから、中の電場(Enet)は 0 にならない。
すなわち絶縁体の中では電場が残る= 電気を通しにくい性質につながっています。
まとめると…
- 導体:中の電子が動いて、外の電場を打ち消せる → Enet = 0
- 絶縁体:電子が動けず、電場を打ち消せない → Enet ≠ 0
図は、「電気を通す・通さない」の違いが、電子の自由度と電場の中の様子に表れていることを、ものすごくシンプルに見せてくれてるんです!
導体と絶縁体の見分け方
日常生活で見かけるもので、「これって導体かな?」って迷うこともありますよね。そんなときのために、代表的な例をチェック!
導体の例
- 銅(電線)
- アルミニウム(アルミホイル)
- 鉄、金、銀(全部金属!)
絶縁体の例
- プラスチック(コードの外側)
- ゴム(電線のカバー)
- 木やガラス(普通は電気通さない)
身近なもので試してみたいときは、電池と豆電球を使って導通テストするのも楽しいですよ!
導体って言葉、難しく感じるかもしれねぇが、実は「電気が通りやすい素材」のことを言ってるだけなんだ。電気を流す上で絶対に欠かせねぇ存在だから、絶縁体とセットでバッチリ覚えとけよ!
|
|
|

